本ページにはプロモーションが含まれています
カーネーションを育てていると、アブラムシやハダニ、ヨトウムシといった虫の発生に頭を悩ませることがあるかもしれません。大切なカーネーションを虫から守り、美しい花を咲かせ続けるためには、適切な駆除方法や予防策を知ることが大切です。葉の裏に潜む小さな虫の対処法から、特定の薬剤、さらには木酢液のような自然素材を活用した虫除けの方法、そしておすすめのスプレーまで、様々な方法があります。
本記事では、カーネーションの害虫問題に直面した際に役立つ、具体的な対策方法を詳しくご紹介します。害虫を水で洗い流すといった手軽な方法から専門的な知識まで、幅広く解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
カーネーションの虫、効果的な駆除方法とは

hanagiftologyイメージ
- アブラムシの発見と対策
- ハダニの被害と葉裏虫対策
- ヨトウムシの夜間の活動と駆除方法
- 害虫対策の予防 おすすめ
- 害虫を水で洗い流す方法
アブラムシの発見と対策

アブラムシは、カーネーションの新芽や若い葉、蕾に群生し、植物の汁液を吸い取ることで株を弱らせる一般的な害虫です。アブラムシの体色は黄緑色から黒褐色まで様々ですが、黄緑色のものが多く見られます。アリが植物の茎を上り下りしている場合、アブラムシの存在を示すサインであることもあります。アブラムシはウイルス病を媒介したり、排泄物によってすす病を誘発したりすることもあります。そのため、早期の発見と対策が非常に大切です。
発見時の対処法
アブラムシを早期に発見した場合は、セロハンテープなどで物理的に取り除くことができます。数が少ないうちは、この方法で十分対応できるでしょう。大量に発生してしまった場合には、薬剤の使用を検討してください。カーネーションや花卉類に登録のある農薬を選ぶと安心です。
予防策
アブラムシの発生は、窒素肥料の過剰な施用によって促進されることがあります。追肥の際には、リン酸が高めの肥料を選ぶと発生を抑えることが期待できます。また、4月から6月、9月から10月はアブラムシの発生が活発になる時期です。この時期の少し前に、特定防除資材である「酢」を原料とした製品を散布すると、予防効果が期待できるとされています。風通しの良い場所で管理し、黄色に誘引される性質を利用して黄色の粘着テープを吊るすことも予防に役立つでしょう。
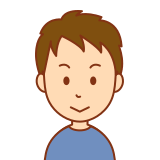
カーネーションの肥料おすすめを知りたい方はこちらをクリック
ハダニの被害と葉 裏 虫対策

ハダニは0.5mmほどの非常に小さな害虫で、主に葉の裏に寄生し、植物の汁を吸います。その結果、葉の表面に針先でつついたような白い小さな斑点が現れ、被害が進行すると葉全体が白くかすり状に変色してしまいます。さらに、ハダニはクモの仲間であるため、数が増えると葉の間に細かい糸を張ることもあります。ハダニは高温で乾燥した環境を好むため、梅雨明けから9月頃にかけて繁殖が旺盛になる傾向があります。特に雨の当たらないベランダなどで発生しやすいです。
発見と確認方法
葉の裏に白い紙を置き、息を吹きかけてみてください。もし小さな虫が動き回るのが見えたら、それはハダニである可能性が高いです。また、葉に糸が絡んでいる場合もハダニの可能性があります。
葉裏の徹底対策
ハダニは水に弱い性質があります。そのため、予防策として、こまめに葉の表裏に水をかける「葉水」が有効です。霧吹きなどを使って、特に葉の裏側までしっかりと水が行き渡るようにすることが重要です。
駆除方法
もしハダニが発生してしまったら、水で洗い流すことが効果的です。葉の裏側まで勢いよく水をかけ、ハダニを物理的に落とします。前述の通り、数が多く発生している場合は、ハダニに効果があるとされる食品原料生まれのスプレーを使用することもおすすめです。薬剤抵抗性を避けるためにも、異なる系統の殺ダニ剤をローテーションで使用したり、カブリダニなどの天敵を利用することも有効な対策となります。
ヨトウムシの夜間の活動と駆除方法

ヨトウムシはヨトウガの幼虫であり、「夜盗虫」の名の通り主に夜間に活動し、植物に大きな食害をもたらします。体長は約20~40mmで、体色は緑色や褐色が多いです。昼間は土の中や葉の裏に隠れているため、なかなか姿を見つけにくいですが、一夜にして葉が大量に食べられているといった被害が見られたら、ヨトウムシの仕業である可能性が高いでしょう。葉にかじられた跡のような穴が開いたり、葉が薄皮だけになって白っぽく変色したり、黒い粒状の糞が見られたりすることが特徴です。4月から6月、9月から11月に活動が活発になります。
駆除と対策
孵化したての幼虫は葉裏に群生していることが多いため、この段階で発見し、捕殺することが最も効果的です。大きくなると薬剤が効きにくくなるため、若齢幼虫のうちに防除することが鍵となります。
夜間に懐中電灯を持って植物を観察し、活動中のヨトウムシを捕殺する方法も有効です。また、誘殺剤やヨトウムシに特化した殺虫剤を使用することも検討してください。
予防策
ヨトウガが卵を産みつけるのは3月から5月です。卵は乳白色で2cm四方くらいの塊となって葉の裏などに産み付けられます。これらを見つけたら、葉ごと取り除くようにすると、被害の拡大を防ぐことができます。浸透移行性の殺虫剤をあらかじめ土に混ぜておくことも予防に繋がるでしょう。
害虫対策の予防 おすすめ

カーネーションを健康に保つためには、害虫が発生する前に適切な予防策を講じることが重要です。予防は、駆除に比べて植物への負担が少なく、手間も抑えられることが多いからです。ここでは、効果的な予防策をいくつかご紹介します。
栽培環境の整備
まず、カーネーションを育てる場所の環境を整えることが大切です。カーネーションは日当たりと風通しを好みます。植え付けの際には、株と株の間隔を適切に保ち、風通しが悪くならないようにしてください。混み合った枝や古くなった葉があれば、適宜切り取り、風通しを良くしておきましょう。これにより、多湿による病気や害虫の発生を抑えることができます。
適切な水やりと肥料
土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えることが基本ですが、水の与えすぎは根腐れの原因となり、植物を弱らせて害虫を引き寄せやすくします。多湿を避けるため、受け皿にたまった水はこまめに捨てるようにしましょう。
肥料についても、与えすぎは禁物です。特に窒素肥料の過多はアブラムシの発生を促すことがあります。生育期にはバランスの取れた肥料を適量与え、真夏や真冬の株が弱りがちな時期は肥料を控えることが大切です。
日常的な観察
日々、植物の様子をよく観察することも重要な予防策です。葉の表裏や茎、蕾などに異変がないか、小さな虫がついていないか、食害の跡がないかなどをこまめにチェックしてください。早期に異変を発見できれば、被害が広がる前に対応できます。
物理的・生物的予防策
黄色の粘着テープはアブラムシの誘引に、青色の粘着テープはアザミウマの誘引に効果があるとされています。これらを吊るしておくことで、害虫の発生を初期段階で捕らえることができます。また、テントウムシなどの天敵はアブラムシを捕食するため、農薬の使用を抑え、自然の力を活用することも予防に繋がるでしょう。
害虫を水で洗い流す方法

特定の害虫、特にハダニやアブラムシに対しては、水を勢いよくかけることで物理的に洗い流す方法が効果的です。この方法は薬剤を使いたくない場合や、害虫の数がまだ少ない初期段階に特に有効です。
水洗い手順
ホースの水をやや強めにして、葉の表だけでなく、特にハダニやアブラムシが隠れやすい葉の裏側にもしっかりと水を当ててください。シャワーのように全体を洗い流すイメージで行うと、効果的に害虫を落とすことができます。
注意点
水洗いを行う時間帯には注意が必要です。日中の暑い時間帯に水やりや葉水を行うと、葉に残った水滴がレンズの役割を果たし、葉焼けを起こす可能性があります。早朝や夕方など、比較的涼しい時間帯に行うようにしましょう。また、植物の株元に水がたまりすぎないよう、水はけの良い土壌環境を保つことも大切です。過湿は根腐れの原因となるため、水洗い後は土の乾燥状態を確認してください。繰り返し行うことで、害虫の数を減らし、被害の拡大を防ぐことが期待できます。
カーネーションの虫除けと病気予防

hanagiftologyイメージ
- 木酢液の効果と利用方法
- 自然素材を活用した虫除け
- 予防と駆除に役立つ薬剤
- おすすめのスプレーと使い方
- カーネーションの病気と対策
木酢液の効果と利用方法

木酢液は、木炭を製造する際に発生する水蒸気を冷却して得られる液体です。この液体には有機酸やアルコール、フェノール類など200種以上の成分が含まれており、農業用途で様々な効果が期待できるとされています。カーネーションの栽培においても、害虫予防、病気予防、土壌改良、そして植物の成長促進に活用できるでしょう。
木酢液の主な効果
-
害虫予防: 木酢液の独特な焦げたような匂いは、アブラムシやハダニ、センチュウなどの害虫を遠ざける忌避効果があると言われています。農場の通路などに散布することも有効です。
-
病気予防: うどんこ病やモザイク病、いもち病など、カビや細菌が原因で発生する植物の病気の予防に役立つとされています。定期的な葉面散布が推奨されます。
-
土壌改良: 土壌に散布することで、土中の微生物活動が促進され、土壌が健康な有機質を豊富に含む状態に改善されることが期待できます。
-
植物の成長促進: 植物の生理代謝を促進し、葉や茎を丈夫にし、花の色を鮮やかにする効果も期待できると言われています。
-
消臭効果: 堆肥の匂いや植物の匂いを軽減する効果も期待できます。
使用方法と注意点
木酢液は原液で使用すると植物を枯らしてしまう可能性があるため、必ず水で希釈して使用してください。一般的に、害虫予防のための葉面散布には1000倍以上に希釈した木酢液を、土壌改良や成長促進には1000倍以上に希釈したものを水やり代わりに土壌に散布することが推奨されています。土壌改良目的で濃い濃度を使用する場合、20〜30倍希釈液を土壌に散布するという情報もみられます。
使用する際は、目立たない場所で少量試してから全体に使用することをおすすめします。また、木酢液は酸性のため、金属製の容器に入れると腐食させる可能性があります。ガラス瓶やプラスチック製の容器で保管するようにしましょう。直射日光を避けて冷暗所で保管することも品質保持のために重要です。
おすすめなのは国産の広葉樹を原料としている木酢液です。
国産の広葉樹を原料とした木酢液がおすすめの理由
-
品質の高さ: データによると、広葉樹(クヌギ、ナラ、ブナなど)から作られた木酢液は質が良いとされています。国産品であれば、原料のトレーサビリティも明確な場合が多く、より安心して使用できます。
-
安全性の考慮: 建築資材の廃材や、有害な成分を含む植物(ウルシ、ハゼノキなど)を原料とする木酢液は避けるべきです。国産の広葉樹を明記している製品は、こうしたリスクが低いと考えられます。
-
透明度とpH値: 一般的に、品質の良い木酢液は透明度が高く、pH値が2.8から3.2の間に収まっているとされています。国産で原料にこだわっている製品は、これらの品質基準を満たしている可能性が高いです。
自然素材を活用した虫除け

薬剤の使用を避けたい場合や、より環境に優しい方法を求める方には、自然素材を活用した虫除けがおすすめです。特定の植物の香りが害虫を遠ざける効果を持つことが知られています。
ハーブの活用
例えば、レモンユーカリやレモングラスには、蚊が嫌がるシトロネラールやシトラールといった成分が含まれています。ラベンダーのリナロールは蚊やハエ、ガを寄せ付けにくいとされます。タイムのチモールは蚊やハエ、ナメクジ、ゴキブリの忌避効果が期待できます。ミントのメントールはゴキブリやハチ、アリの虫除けに有効とされ、ローズマリーのカンファーは衣類の防虫剤としても活用される成分です。
これらのハーブをカーネーションの近くに植える「コンパニオンプランツ」として利用することで、自然な虫除け効果が期待できます。鉢植えのハーブを置いたり、庭に地植えしたりする方法があります。また、乾燥させたハーブを使ってサシェを作ったり、煮出してスプレーを作ったりすることも可能です。
その他の自然由来成分
牛乳を薄めてスプレーする方法もアブラムシに効果があると言われていますが、これからの季節は腐敗による悪臭やカビの発生に注意が必要です。
特定防除資材の「酢」を原料とした製品は、アブラムシやハダニの予防に利用できます。例えば、フマキラーの「カダンセーフ」やアース製薬の「やさお酢」は食品由来の成分で作られており、比較的安心して使用できる自然素材の選択肢です。
予防と駆除に役立つ薬剤

害虫や病気の発生状況によっては、薬剤の使用が最も効果的な対策となる場合があります。しかし、薬剤を選ぶ際には、その効果だけでなく、使用方法や安全面への配慮が不可欠です。
薬剤の選び方
薬剤を選ぶ際は、まずカーネーションに適用があるかを必ず確認しましょう。害虫の種類や病気の原因に合わせて、適切な殺虫剤または殺菌剤を選びます。
具体的な商品例
いくつかの薬剤を例に挙げます。
-
オルトラン粒剤(GFオルトラン粒剤など):これはアブラムシやヨトウムシなど幅広い害虫に効果がある浸透移行性の殺虫剤です。土に混ぜて使うタイプなので、根から成分が吸収され、植物全体に効果が行き渡ります。
-
ベニカXネクストスプレー:アブラムシ、ハダニ、アオムシなど多くの害虫に効果があり、うどんこ病や黒星病といった病気にも効く殺虫殺菌剤です。スプレータイプで手軽に使えます。
-
ダコニール1000: さまざまな植物の広範囲の病気に効果がある殺菌剤です。灰色かび病やうどんこ病などの予防・治療に使えます。
使用上の注意点
薬剤を使う際は、必ず製品の取扱説明書をよく読み、記載されている使用方法や希釈倍率、使用時期、使用回数を厳守してください。間違った使い方をすると、植物に薬害が出たり、効果が薄れたりするだけでなく、環境や人体に影響を及ぼす可能性もあります。
散布する時は、農薬用マスクや手袋、長ズボン、長袖の作業着を着用しましょう。風向きを考え、周囲の家屋や洗濯物、ペットなどに薬剤がかからないように注意することも大切です。ミツバチや蚕に影響を与える薬剤もあるため、そういった注意書きがないかも確認してください。
また、同じ薬剤を使い続けると、害虫や病原菌に薬剤への抵抗力がついてしまうことがあります。これを防ぐために、異なる有効成分の薬剤をローテーションで使うことをおすすめします。
おすすめのスプレーと使い方

手軽に使えるスプレータイプの薬剤は、初心者の方にもおすすめです。様々な製品がありますが、ここではいくつか代表的なものと使い方をご紹介します。
ベニカナチュラルスプレー
この製品は、還元澱粉糖化物、調合油、バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素という3つの天然由来成分が配合されています。アブラムシ、ハダニ、うどんこ病に効果があり、チョウ目の幼虫(アオムシ、ヨトウムシ、ケムシなど)にも効果が期待できるとされています。食べる直前まで使用できるという特徴があります。
使い方: 使用前には容器を数回振ってください。葉の表裏にムラなく薬液がかかるように丁寧に散布します。チョウ目の幼虫には、若齢幼虫期に散布することが有効とされています。病害虫の増殖が活発な場合は、5~7日間隔での連続散布が望ましいでしょう。
カダンセーフ(ソルビタン脂肪酸エステル製剤)
この殺虫剤は、デンプン由来の糖とヤシ油の成分で作られており、食品から作られているとされています。虫が呼吸する穴(気門)をふさぐことで窒息死させる作用があり、薬剤抵抗性が発生しにくいというメリットがあります。ハダニにも効果が期待できます。
使い方: 散布することで花弁が傷む可能性があるため、開花した花やつぼみは摘み取ってから散布した方が、薬液が隅々まで行き渡り効果が高いとされています。
やさお酢(特定防除資材)
上記で説明した通り、「酢」を原料とした殺虫殺菌剤です。アブラムシ類やうどんこ病、灰色かび病などに効果が期待できます。食酢が主成分なので、化学合成農薬を使いたくない場合に適しています。
使い方: 薄めずにそのまま使えるスプレータイプが多いです。アブラムシ類の発生が特に増える時期の少し前に、予防として散布するのがおすすめです。発生してしまった場合も、カーネーションに登録のある製品を選び、指示に従って散布してください。
これらのスプレーは、手軽に害虫対策ができる点が魅力です。使用する際は、必ず製品の注意事項をよく読み、適切にお使いください。
カーネーションの病気と対策

カーネーションは様々な病気にかかる可能性がありますが、特に注意したいのは灰色かび病、モザイク病、立枯病です。これらの病気からカーネーションを守るためには、適切な予防と早期の対処が重要となります。
灰色かび病
この病気はカビ(糸状菌)が原因で、低温多湿な時期、特に梅雨時や秋の長雨の時期に発生しやすくなります。葉が黒くなったり、花が褐色になってシミのような病斑ができ、進行すると葉や花弁が腐敗して枯れてしまいます。灰色の粉(分生子)が生じ、他の株への伝染源となることもあるため、早めの防除が必要になります。
対処法:
-
予防: 風通しを良くし、咲き終わった花がらや枯れ葉をこまめに取り除くことが大切です。水やりは花や葉に直接水がかからないように注意してください。特定防除資材の「酢」が原料の製品を散布することも予防に役立ちます。
-
治療: 発生初期であれば、症状が出た部分を丁寧に取り除き、様子を見ます。症状が広がる場合は、灰色かび病に登録のある専用の殺菌剤をできるだけ早く使用してください。
モザイク病(ウイルス病)
モザイク病はウイルスが原因で、アブラムシによって媒介されることがほとんどです。初期には若い葉の葉脈が透けるようになり、進行すると緑色の濃淡のあるモザイク症状が現れます。葉が小さくなったり、葉脈が湾曲したり、表面が凸凹になったりすることもあります。
対処法:
-
予防: モザイク病はウイルス病であり、一度感染すると治療が困難なため、媒介するアブラムシの対策が最も重要になります。種子消毒では駆除できないため、アブラムシの発生を徹底的に抑えることが予防の鍵です。感染が疑われる株は、他の株への感染拡大を防ぐため、速やかに抜き取って処分することが推奨されます。
立枯病
カビが原因で発生する土壌病害の一つです。梅雨の時期など雨が続くような時期に特に注意が必要です。下葉から変色し始め、株全体がくたびれたようにしおれて枯れてしまいます。水はけの悪い土壌や連作は病気を引き起こしやすいため、注意が必要です。
対処法:
-
予防: 水はけの良い土壌を使用し、連作を避けることが大切です。植え付けには清潔な用土を使用しましょう。
-
治療: 残念ながら、一度発病した株の回復は難しいことがほとんどです。病気が発生した株は、見つけ次第抜き取って処分し、隣の株への被害拡大を防ぐことが重要です。必要に応じて土壌の入れ替えや消毒を検討してください。


